私は二人の子供を育てる36歳ワーママ。
子供たちは3歳と8歳の女の子です。
昨年の夏の終わり、同い年の36歳夫が大腸癌ステージ4と宣告されました。
まだまだ治療中で何かを成し遂げたわけではなく、「治療」「お金」「仕事」「目の前の育児」「先の教育」様々な課題と不安と直面しながら模索している毎日です。
ひとつ確かな事は「わからないことに立ち向かう事は強いストレスになる」という事です。
同じような経験をされた方のお役に立てればと思い、診断からの6か月間の日々、この記事では特に濃厚だった最初の1か月についてお話しようと思います。
癌はどうして発覚した?きっかけは健康診断の「便潜血+
大腸カメラの予約を取りに行くつもりの受診で「緊急入院」
癌が発覚したのは、会社の健康診断の結果で「便潜血」に引っかかり、要精密検査となった事がきっかけでした。
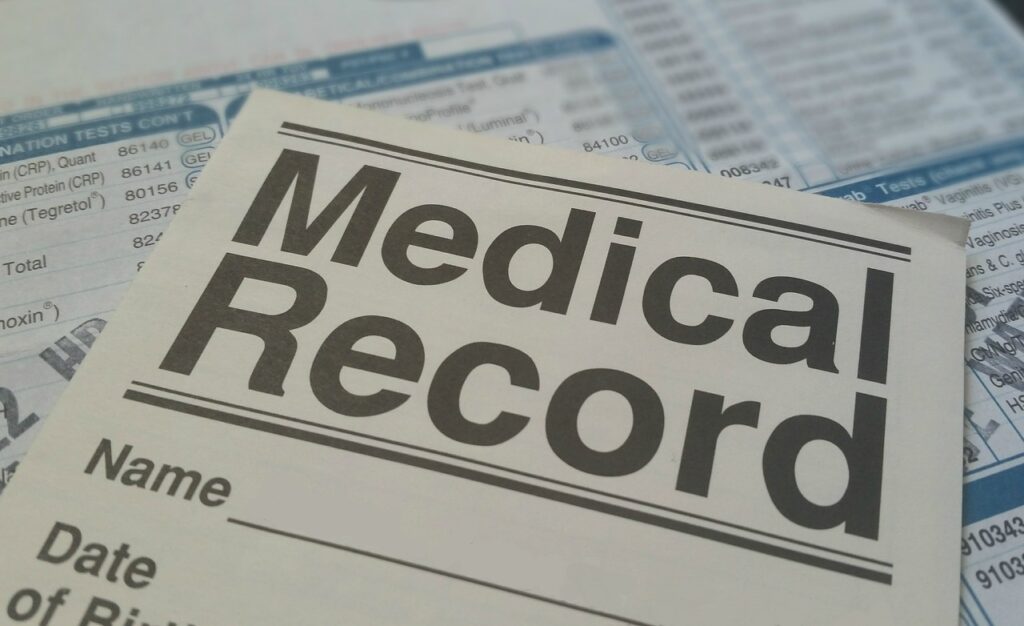
この日は、朝から「今日、健康診断の再検査いってくるわ」と、下の娘の保育園の支度をしながら、ついでのように夫が伝えてきました。
私は小学校へ通う上の娘を送り出しながら話を聞いていました。
「え、何か引っかかったの?」と、この時に初めて夫が健康診断で指摘された事を知りました。
両家とも実家が遠方にあり、援軍無しで子育てとそれぞれの仕事を回すことに日々精一杯な状態で、互いの健康状態にまで気持ちが回っていませんでした。
そしてお互いにバタバタと出かけて。昼頃に連絡が来ました。
「緊急入院になりました」と。
驚きと共に、血の気が引いたことを覚えています。
腫瘍が見つかり、それが良性か悪性かで今後の対応が変わるとの事でした。
悪性の腫瘍、それは、つまり「癌」を意味していました。
なぜすぐに診てもらえたのか?問診時の「便の異変」で医師が判断
健康診断などで大きな病院に紹介状が出た場合、通常であれば一回目の外来では問診で終了し、次回に大腸カメラの予約を取る、という事が多いそうです。
では、なぜ、大きな自覚症状が無かったのに夫は一度目の受診で緊急入院になったのでしょうか。
決め手となったのは、「便をする際におなかが痛く、便が細い」という症状。この症状を、医師に伝えられた事でした。
そして、帰り際のこの発言に引っかかり、夫を呼び止め、CTを撮影する事にしてくれた医師のスーパーファインプレーでした。
もし、この時に発覚しなかったら、もっともっと進行した状態での発覚となった事かと思います。
少しでも異変を感じたら、「こんな事」と思わずに伝えてください。
素人にはわからなくても重要な病気のサインかもしれません。
発覚からの6か月 何をして過ごしてきたか

この6か月間の足取りです。
見ての通りですが、1か月目は猛烈にやる事が多かったです。
それはもう、本当に猛烈に濃厚で濃密な日々でした。
逆に、治療方針と手術を行う病院、その後の抗がん剤治療を行う病院が決定した2か月目以降は、比較的穏やかに時間が流れていきました。
ポイントとなった1か月目、ここを細かく見ていきたいと思います。
画像診断と内視鏡での所見
緊急入院した日の夜に病棟の主治医の先生から画像診断の段階で「十中八九悪性の腫瘍だと思う」と告げられました。
確定診断は出ていない状態で、十中八九と医師に告げられる。
この時点でもう、悪性である事は確定だと感じました。それと同時に、進行度として決して初期ではない状態なのだと察しました。
入院して内科的処置を進める
腫瘍が悪性か良性かの判断が確定する前に、やるべきことがありました。
この時の夫は、腫瘍が大きくなり、大腸が「腸閉塞」を起こしている状態。

この状態をとりあえず落ち着けるために、腸内にステントという金属を入れて、狭くなっている箇所を広げる、という処置が必要でした。
内視鏡を使っての処置で、ステントの処置が終わり、便の通りが良くなるとこの段階での処置は終了です。
食事をとって大丈夫な状態になったタイミングで退院となりました。
治療方針と病院の選定
一口に「癌」と言っても、罹患している箇所や状態によって治療方針は大きく異なります。
あくまで、夫の場合の話として受け止めていただきたいと思います。
夫の場合は、原発巣(がんが最初に発生した場所)に加えて、周辺のリンパにも転移が見られました。
そして、周辺よりも遠い位置のリンパにも転移を疑う所見がありました。
治療の決め手となりそうなのがこの遠隔リンパへ転移があるか、ということでした。
・「遠隔リンパ」に転移があるか否か
・転移である場合、手術で取り除くことが出来るのかどうか
・手術を行う場合、開腹手術か腹腔鏡手術か
・ロボット手術は適用できるかどうか
この辺りが治療方針を決める大きなポイントでした。
私たちは人口20万人の地方都市住まい。受診した病院も、その地方にある病院です。
主治医の先生から、手術に関しては転院を勧められ、いくつかの候補をあげてもらいました。
私たちは、病院の情報を持ち合わせていなかったためすぐに「じゃ、ここにします」と決められませんでした。
ここから最も頭と心をすり減らした「転院先の選定」の段階へ進みました。
情報収集は「近隣住民」と「専門職・業界の人」に聞く
とても幸運な事に、私の職場には祖父母以上の代からこの土地に住んで生活している人が多く、病院の情報に詳しい同僚がいました。
信頼できる職場の同僚数名に話をして、この辺りの病院事情、ご親族や知人の方の体験談などを教えていただきました。
それと同時に、近隣には住んでいませんでしたが、医療従事者の友人・知人たちにも意見を聞きました。
一人に聞くのではなく、複数人の、いくつかの立場からの意見を聞く。

こうすることで、誰かの意見を鵜呑みにするのではなく最終的には「自分たちの決断」として決定する事が出来ました。
実際に候補の病院へ足を運んでみて、現実的に通院が可能か、病院の雰囲気などを確かめたり、相談窓口で話を聞いたりして少しずつ候補を絞っていきました。
そして、候補となる病院を決めて、主治医に伝えることで紹介状を書いてもらい、実際に受診して手術の予定を取る事が出来ました。
手術予定が決まったのにセカンドオピニオン?
この病院巡りや検討の日々は私ひとりで行ったものではありません。
前職で医療業界にいた私の兄が協力してくれて、病院巡りに同行してくれたり知恵を貸してくれていました。
とても感謝しています。
最終的に決めた病院では、「開腹手術にて転移が疑われる箇所は遠隔リンパも含めてすべて取り除く」という方針になっていました。
医師が夫の年齢等を考慮して、なるべく早めに手術をするためにこのような方針を組んでくれていました。
しかし、医療業界にいた兄は少し気がかりだったようで、夫が病院を決めた後もこっそり情報収集を続けていました。

この頃は、私自身も疲労が蓄積しており、早くこの日々から逃れたいという思いがあって、たどり着いた解決策が「最善」で、「これが全て」なんだと思いたい、という気持ちがあったのかもしれません。
数日後、兄から連絡がありました。
「やっぱり、セカンドオピニオンを受けてみないか?」と。
転院先も決まって、手術の日程も抑えたのに?と思いました。
なんなら、転院先もセカンドオピニオンで決めた病院です。
兄曰く、この病気の権威と呼ばれる先生が隣の県の病院にいて、その先生のセカンドオピニオンがオンラインで受けられるとの事でした。
もし、いま決めている病院と見立てが同じで、同様の手術になるなら今のままでもいいし、万が一別の治療方法やアプローチになるのであれば検討の余地があるかもしれない、と。
この時の私は、正直、検討疲れ・選択疲れで「ちょっと無理…」と言いたいのが本音でした。
しかし、オンラインでのセカンドオピニオンなので、遠方に住んでいる兄も無理なく参加できます。説明や対応、事務的な事も請け負ってくれると申し出てくれたのです。
夫に話をすると、彼も同様に心身の負担が大きい日々だったので「ちょっと無理…」と本音では言いたげでしたが、義理兄の好意を無下にできないと感じたのか「お願いしよう」ということになりました。
転院先の最終決定|まさかの全く異なる選択肢
結論から言うと、このセカンドオピニオンにより、夫は転院先をさらに変更しました。
見立て、手術手法、アプローチが2番目の病院と異なっていたからです。
どちらが正解でどちらが間違いというわけではなく、「異なる意見」が出てきて、「異なる選択肢」を選べるようになったのです。
セカンドオピニオンという制度は耳にしたことがある方も多いと思います。
「セカンド」という位なので、今いる病院の次の病院の検討のため、と思う方もいるかもしれませんが、「何回やってもOK」1回限りの必殺技ではないのです。
もちろん、その分の労力や金銭的な負担は生じますが、主治医や、転院先の医師に必要以上に遠慮する必要は一切ありません。(たまにムッとする医師もいるそうですが、そこは気にしなくていいよと知人の医師に言われました。)
ただし、むやみに何か所も意見を聞く事で治療が遅れてしまうというリスクがあるので、本当に必要であれば活用する、とお考え下さい。
実際に、転院先を再度変えた事により、当初の手術予定日より二週間、実施が遅くなりました。
しかし、進行のリスク、術後のQOL等を総合的に判断して、私たちは最終的な結論を出すことにしました。
術後、体への負担が少ない方法を選択したため、当初は1か月~2か月といわれていた入院期間は10日間となり、術後の体の傷もとても小さく済みました。
まとめ:最初の「ヤマ」をまずは乗り越えよう
こうして、怒涛の一か月はとてつもない密度と濃度で過ぎていきました。
この最初のヤマ、第1フェーズの期間は病状によって異なると思いますが、ここを乗り越えるとあとは粛々と治療を進める日々に入ります。
患者さん本人はもちろんですが、そばで支える家族にもとても辛く、心が挫けそうになる事かとは思います。
しかし、治療方針や病院の選定は人生に関わる大きな選択になる事かと思います。
とても大事な事なので、なし崩しに決めるのではなく、納得をして選択・決断をしてほしいと思います。
とても辛く苦しいフェーズではありますが、ずっと続くわけではありません。一旦必ず落ち着きます。
どうか、まずはこのフェーズを乗り越えていただきたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。



