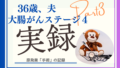こんにちは、私は二人の子供を育てる36歳ワーママ。子供たちは3歳と8歳の女の子です。
昨年の夏の終わり、同い年の36歳夫が大腸癌ステージ4と宣告されました。
怒涛の一か月目を何とかやりこなし、闘病生活二か月目に突入しました。
治療の大きな柱のひとつ、「手術」に挑むちょっと前の、「待期期間」を過ごした記録です。
振り返ると、「手術」「抗がん剤治療」と並ぶくらいに大きなイベントだった「待期期間」。
ここをどう過ごすかは、治療と生活の全体を整えることにとても大きな影響を与えることかと思います。
同じような経験をされた方のお役に立てればと思い、診断からの6か月間の日々、この記事では闘病2か月についてお話しようと思います。
※なお、ここに書いているのはあくまで夫の場合の一例です。同じ病名、ステージであっても状況は異なるので、医師の診断をしっかり仰いでご判断をお願いします。
二か月目のメインイベントは「待機」
想像できていなかった病気発覚からの時間軸
私はこれまで、自分の出産以外では「手術」を伴う入院をしたことがなく、病気が発覚してからどのような時間軸で事が進むのか全く想像が出来ていませんでした。

特に、夫の場合は進行性の癌。
年齢も若く、初診時点でステージ4といわれたわけなので、今すぐにでも手術をしなきゃ命に関わるのでは?と感じていました。
しかし、「癌」「進行性」「若年」の三要素がそろっているからと言って、誰でもすぐに急激に進行するわけではないそうです。
癌が発現している場所、現在の病状、患者の年齢や体力、他の疾患などから、総合的に判断します。
夫の場合であれば「二週間程度手術が先に延ばしになっても、他に転移したり、顕著に病状が進行することは考えにくい」と医師が判断してくれました。
この時間的な猶予があるということは、セカンド(サード?)オピニオン先の病院で、転院を決意した大きな要素でした。
手術までの待機時間は意外と長い
大きな病院では、手術までの待機時間というものが生じます。
オンラインでセカンドオピニオン → 外来受診 → 手術 この過程に約1か月の時間が必要でした。
夫の場合はここに至る前に、最初の病院での入院、ステント処置、セカンドオピニオン(その1)を行い、病気発覚から既に一か月が経過している状態でした。
正直、「ステージ4の癌です」と言われて、手術まで二か月待つ、というのはかなり精神的に負担が大きいです。
本人はもちろんですが、家族も、です。
少し気を抜くと、先が見えない暗闇に落ちてしまいそうな気持になります。
なので、この期間は「自分でコントロール出来る事」「今出来る事」を一つ一つ準備して、こつこつと積み上げていくことにしました。

待機期間に夫がしていた事「口座の集約」
この頃、夫はコツコツと口座の集約と整理を始めました。

夫は病気発覚後にそのまま入院、となったため、夫は会社を休業していました。
そのため、最初の入院が終了し、手術までの待機期間は平日日中にたっぷりと時間がありました。
平日日中に時間があるのなら、平日日中じゃないとできない事をやる。
そこで取った行動が、口座の整理だったそうです。(なかなか筋が良い)
新入社員の時に会社から開くように言われた地銀などの口座を複数休眠させていたこともあり、これを機に解約して集約をしていました。
そんなに多くは無かったのですが、一つの銀行の手続きに移動なども含めて一日仕事となるため、時間つぶしにはもってこいだったようです。
子供の送迎、家事の分担
わが家には3歳の保育園児と、8歳の小学2年生の子供がいます。

加えて、夫婦ともに地元が遠方(飛行機の距離)なので、近隣に親族がいません。
そのため、私たち「親」は風邪でも、熱でも、コロナでも、インフルでも、1日も休むことなく子育てをしてきました。
癌でも同じです。
子供の存在は若年層、現役世代がん治療の辛い所でもあり、支えになる所でもあります。
毎日の保育園の送迎と、学童保育のお迎え、習い事への送迎、掃除、料理、片付け、音読を聞く、計算カードを聞くなどなど、小さなタスクは山ほどありました。
これら全てを夫に丸投げしたわけではありませんが、保育園の送迎を中心に家事をこれまでより少し多めに担ってもらうようにしました。
人と会うのがしんどいと感じるかもしれないと思い「先生たちと会うことはしんどくないか」を確認したところ、問題ないとの事だったので送迎はほぼ全てお任せする事にしました。
会社勤めの社会人は、ともすれば「仕事」から離れると社会から寸断される危険があります。

長女の育児休業中に、私は社会から孤立した気持ちになり、一人ぼっちになったような寂しさに襲われた経験がありました。
子供たちを媒介にして、社会、周囲の人々との繋がりを持ち続けてもらった事は、夫にとっても、子供たちにとってもプラスになったなと感じています。
そして、患者の妻である私にとっても、日々の精神的な疲れと家事・育児・仕事の疲れから少し解放されて、とても助けになりました。
「好きな事してゆっくり過ごす」は結構ハードルが高い
「時間が取れるんだから、ゆっくりしたり好きな事をしなよ」と考える方もいると思いますが、これは意外とハードルが高いのです。
「健康」と「未来」というかけがえのないもの、そして夫の場合は3歳と8歳の娘がいるため「子供との日々」を失うかもしれないという状況です。
こういう時は、ゆっくりしたり出来ないモノなのです。
また、不思議な事に一番好きな事が出来なくなったりするのです。

そのため、タスクを積み上げて粛々とこなしている方が精神的に安定したりするものです。
もし、身の回りに病気等で大切なモノを「喪失」した方がいた場合、安易に「好きな事してゆっくり過ごしてね」と声をかけるのはあまりベターではないかもしれないです。
笑顔で「ありがとう」と答えてくれると思いますが「したくても出来ない」というのが本音かもしれません。
声掛け自体はとても喜ばれると思うので、体や心を気遣うものが良いかと思います。
「思いっきり楽しいイベント」を用意した
では、楽しい事、好きな事は何もできないのかというとそうではありません。
本人が主体で、日々小さな「楽しい事」を探すのは難しくても、周りの人が「思いっきり楽しい事」に引きずりこむことは可能です。
私たち家族は、この待期期間に夢だった「家族でディズニー旅行へ行く」を実現させました。

コロナ禍や下の娘の妊娠出産など、様々な理由で先延ばしになっていた我が家の夢。ここで実現させることにしました。
様々な事情を考慮して、バケーションパッケージを利用することにして、ホテルミラコスタのハーバービューの部屋を確保し、ディズニーランドとシーを待ち時間なしで大満喫するプランを組みました。
・平日に時間がある
・手術前で体力がある
・子供たちと楽しい時間を過ごしたい
これらをすべて掛け合わせた結果、ディズニーに行く事にしました。
行くと決めたその日から、夫婦の会話の7割は旅行のプラン決めとなり、待機期間の前半分はディズニーの計画、あと半分はディズニーの思い出話となり、とても良い時間を過ごすことができました。
やることが決まって、何もできない期間がある場合は、思いっきり現実逃避をするのもありだと思います。
まとめ:良い待期期間を過ごして治療に全力で臨もう
待機時間は意外と長くて、しんどいけれど、とても重要な時間です。
この時間をどう過ごすかは、治療全体のクオリティに影響を与える事かと思います。
夫の場合は、待期期間を経て、手術、抗がん剤治療とコマを進めていますが、この待期期間を充実させたことで、現在の生活をしっかり受け止めて治療に臨むことが出来ているようです。
それと共に家族共通の最高に楽しい思い出が作れて「もう一回みんなでディズニーに行く」という家族全員の目標が生まれました。
「出来るタスクをコツコツとこなしつつ、思いっきり現実逃避」これがわが家の待期期間の過ごし方でした。
どなたかの参考になれば嬉しいです、最後までお読みいただきありがとうございました。