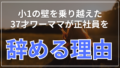働く理由は様々あると思いますが、まずは「生きていくため」である事が一つ目の理由です。
わが家には小学生と保育園児の子供がいるため、自分が生きていくためという事はもちろん、子供たちを育てていくためにお金が必要です。
では、その収入の柱であった「仕事」を辞めた場合、どうなるんだろう、やっていけるのかな。
そんな不安を抱きました。
なので、まずは「お金の不安」を可視化しようと考えました!
今日は「家族が生きていくために必要なお金」を考える方法についてお話したいと思います。
自分が仕事を辞めたら家計はどうなるかを考える

自分の今の給料がなくなった時のシミュレーションを2パターン考えたよ

2パターンってどういうこと?

①夫が定年まで元気に働ける
②万が一の事があって夫に収入がなくなる
この2パターンを考えたよ
夫が元気に仕事を続けるパターン
夫が現在の仕事を元気に続ける、という想定で試算をします。
給与の伸びに関してはざっくりと、少し低めに見積もりました。
退職年齢については現在会社から発表されている年齢とし、退職金についても会社の規定から算出して、定年まで働いた時の金額をざっくり試算します。
まずは毎月の収入をざっくり把握する、という感じでいいと思います。
万が一の事があり自分の一馬力になるパターン
こちらは「なんて不謹慎な!」と気分を悪くされる方もいるかもしれません。
しかし、いつ何があるかわからないのが人生です。
子どもがお金がかかる頃(上の娘が中学生ごろと設定しました)に亡くなってしまう、という想定で、会社の給与がなくなる場合を想定してみました。
加入している生命保険からいくら出るのかを把握する
もし夫が亡くなったとして。
現在加入している生命保険からいくら保険金がもらえるのかを把握してみました。

結婚した時に入ったけど、詳しい保証内容は正直よくわかってないなぁ…
もし、補償内容が良く分かっていないという場合は、一度保険証券を確認する事をおすすめします。
生命保険金はおそらく大きな収入の柱のひとつになると思います。
現在加入している保険を確認する事で、「そもそもこんな保険にも入っていたのか」と掘り出し物があるかもしれません。
公的制度(社会保障)でいくらもらえるのかを把握する
日本の社会保険制度はとても保証が手厚いです。
「公的年金」というと、年を取った時に貰える「老齢年金」をイメージすることが多いと思います。
しかし、日本の公的年金は「老齢年金」「遺族年金」「障害年金」の三つの柱で成り立っています。
もし、会社員の夫が現役世代で亡くなった場合は「遺族年金」の「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」を貰う事が出来るそうです。

なるほど、夫に万が一になった時も収入はゼロになるわけではないんだね
厚生年金に加入しているかどうか、子の人数や年齢、妻の年齢など細かく取得の条件があるため、一概にいくら、と試算をするのが難しいのですが子どもが2人いる家庭だとざっくり14万円くらいの金額を子が18歳になるまでは貰えるとのことです。
現在の生活費についてまずはデータを取る

それぞれ収入を把握したからそこから生活費を引くといくら足りないかがわかるんだね

そのとおり!さすがだね!

でも、生活費っていくらで見積もればいいんだろう?
(公財)生命保険文化センター「令和3年度 生命保険に関する全国実態調査」にて、遺族の生活に必要な資金額として世帯年収別に資産がされています。
しかし、どの世帯収入でもざっくり月額30万円という所でしょうか。
現在加入している生命保険金と、遺族年金、そこからこの生活費約30万円を差し引く事で、月々の生活にいくら金額が足りないのか試算することが出来ます。
しかし、この「生活費30万円」という金額。これが本当にご自身の生活に当てはまるのか。
それは実際に確かめてみないとわかりません。
将来いくら必要になるかの試算にはまずは現状把握が必要
家計簿を既につけているご家庭であれば、そこから月々の生活費を把握することが可能です。
もし、現在家計簿をつけていないということであれば、家計簿アプリなどを用いて家計費を一度抜けもれなく把握してみる事をお勧めします!
共働きで子育て中の世帯であれば、想像しているよりもお子さんの習い事や食費にお金がかかっている場合もあります。
わが家は時短のためにキットになった食材や、加工済みでレンジでチンするだけの冷凍商材をネットで購入していたため、一般家庭よりも食費が多くかかっていました。
また、習い事費用もなかなかのものになっていました。
家計簿アプリ「マネーフォワードME」がおすすめ
私は結婚してから10年間、紙のノートに家計簿をつけていました。
買い物の後には必ずレシートを貰い、それをコツコツ書く。あれ?でもこれって食費だっけ?日用品?
カードで支払ったときって購入した日を書く?それとも口座からお金が落ちる日??
そんな小さな疑問をぽろぽろ取りこぼしながら、とりあえず「書くことに意義がある」と自分に言い聞かせて出来る範囲でやっていました。
しかし、抜け漏れの多い家計簿では家計の把握はできないし、資産計画なしにはお金はたまりません。
完全に無駄だったとは言えませんが、お金のたまらない家計簿に時間を割いていました。
しかし、「家計簿アプリ マネーフォワードME」を付け始めると、おもしろいほどに簡単に家計簿が出来るようになりました。
苦労して失敗した経験があるので、この有難さと偉大さはすさまじいものだとわかります。
まずは「何にいくら使っているか」を把握するため、無料版のアプリで良いので試しに使ってみる事をお勧めします。
子どもの成長に合わせた教育費を見積もる
人生の三大支出といわれるのが、「住宅資金」「教育資金」「老後資金」です。
「住宅資金」は現在既に生活費の中に組み込まれていたので、一旦ここはステイ。
わが家では「教育資金」に重きを置きたいという思いがあるため、ここがどの程度必要となるかを試算しました。
- 中学、高校は私立に進学と想定
- 中学受験のための塾の費用
- その他習い事費用
- 国公立大学に進学と想定
想定される範囲でお金を多く使いそうな想定をしてみました。
ちなみに、高校無償化は計算に入れていません。なるべく支出は多めに見積もった方が良いかと思います。
ライフイベントを考える
その他のライフイベントとして、ちょっと大き目なちょこちょこかかる費用を見積もっていきます。
- 車の買い替え費
- 家のメンテナンス費用(外壁、水回りなど)
- 旅行費用
- 家電買い替え費用
- その他医療費等特別費
これらは学資保険の加入の際に、保険屋さんのライフプランナーさんが作成した「ライフプランシート」に入れ込んでいた費用です。
旅行費用や車の費用など、こちらも支出に関しては多めに見積もると良いと思います。
ライフプランシートを作成して「将来のお金」を見積もる

それぞれ考えてみたけど、わかりやすくまとめたり出来ないの?

もちろん出来るよ!ライフプランシートのフォーマットが無料であるからそこに入れ込んでみよう
ライフプランシートのフォーマットは日本FP協会ホームぺージで手に入れる事が出来ますよ。
もちろん無料です^^
ライフプランシートの作成はファイナンシャルプランナーやライフプランナーの資格が無ければ出来ない、なんてことはありません。
日々の生活費と、ライフイベントに必要な金額の目安を自分の中に作っていれば誰にでも作成が可能です。
逆に言うと、日々の生活費、将来のプランが無いと、どんなに優秀なFPさんでもあなたの生活に沿ったライフプランシートを作成することは難しいと思います。
現在の仕事を辞められるか数字から判断する

将来の生活に必要なお金がわかったら、私の場合は正社員でフルタイムの給料じゃなくても大丈夫かもって気がしてきたよ
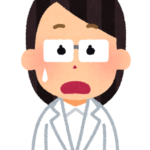
私は逆に不安になったな…生活費が思ったよりも多くかかってたよ…
会社を辞めたいけれど、生活費の不安がある場合は、家計管理に取り組んでみてはどうでしょうか。
日々の買い物でより安いスーパーを探し、電気をこまめに消…すのも重要ですが、それ以上に固定費の削減をしていくと効果が大きいです。
生活費の中で毎月かかっている費用(保険、サブスク、スマホ代、ネット代など)の中で、見直しが出来そうなものから取り組んでみるといいと思います。
大手キャリアから格安SIMに乗り換えるだけで月5,000円×人数分の節約が出来て、家計に与えるインパクトはとても大きいですよ!
家計を把握して、生活費を適正化、そして現在の仕事を辞めることが出来るか、他の働き方に変える事が出来るのか、数字で考えてみると悶々とした日々から一歩抜け出すことが出来ると思います!
最後までお読みいただきありがとうございました!