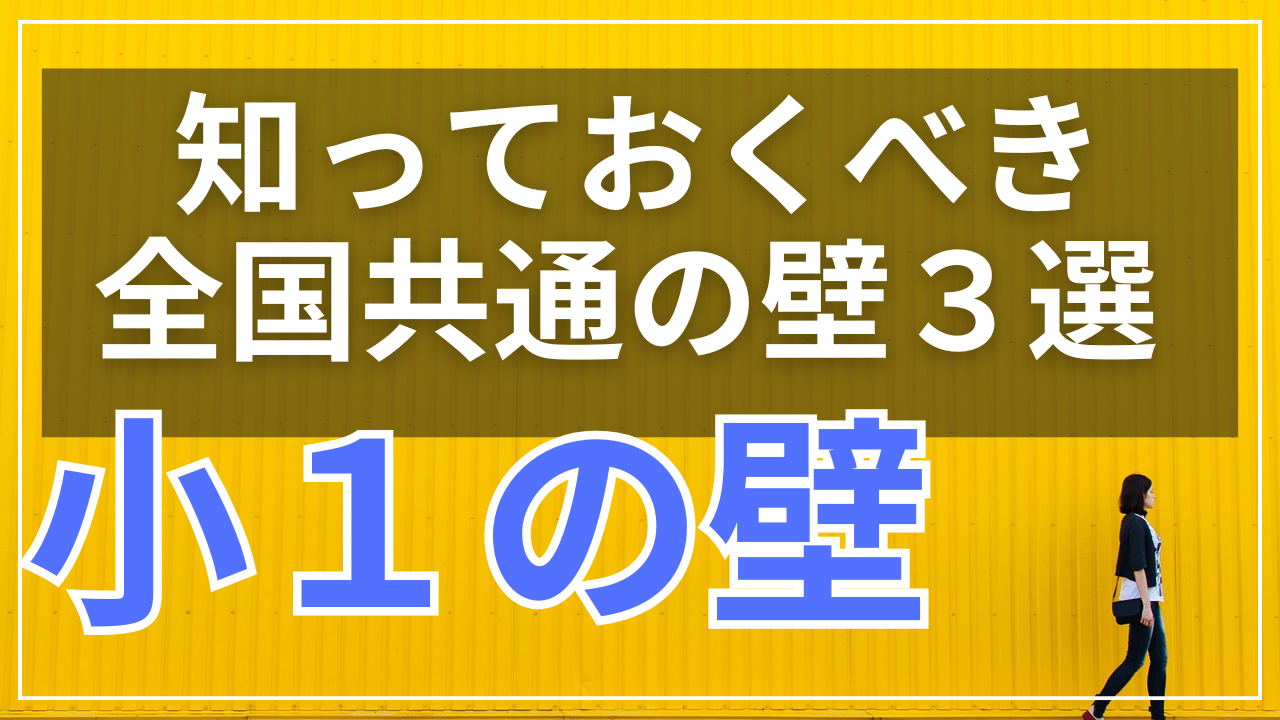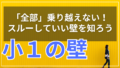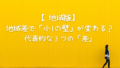スルーしていい壁と向き合うべき壁がある
小1の壁、と一言で言っても立ちはだかる「壁」は様々な種類のものがあります。
その全てをやっつけようとすると、日々忙しい働く母はキャパオーバーになってしまいます。
そのため、スルーしてもいい壁を見つけて、向かい合うべき壁を見極める!その上で対策を練る必要があります。
この記事を読んでいただくと、全国共通で見られる「小1の壁」3つを、リアルな実例と数字で判断する事ができ、ご自身の生活に当てはめたときにどう対策をとるべきか、具体的に考える事が出来るようになると思います。

「これ絶対知っとけ」的な壁を教えてほしいです!

オッケー!まずは地域性がない全国共通の壁を紹介するね!
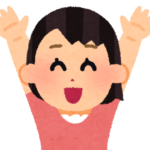
ありがとうごっざいます!!
【全国共通】向き合うべき壁3選
「自立」の壁
小学生と保育園児の大きな違いは「自立を求められる」ことです。
保育園での生活では「自分でできたんだね!偉いね!」という環境でしたが、小学校では自分でするのが当たり前の生活になります。
- 登校と下校
- 授業前後の準備
- 給食の配膳、食べる事、片付け
- 掃除
- 宿題
- 提出物の管理
- お友達とのあれこれ
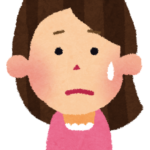
いきなり不安になってきた…うちの子ちゃんと出来るのかな

入学までにパーフェクトに出来るようになる必要はないよ!ボランティアさんや高学年の子たちがサポートしてくれるからゆっくり馴染めば大丈夫!
娘の小学校では給食の準備や配膳、掃除の仕方、夏のプールの授業の際には着替えのサポートをしてくださっていました。
最初から完璧な状態で入学することはおそらくほとんどのお子さんには難しいです。
しかし、こういった事を少しずつやっていく、という心の準備は必要かもしれませんね。
お休みの日に散歩がてら通学路を歩いてみたり、保育園の荷物の片付け(体操服や給食セットを出す)など、今の生活に無理なく組み込める事を少しづつ取り入れてみると良いかもしれません。
「時間」の壁
入学してから情報解禁?下校時間はなかなか早い
初めての環境で緊張や気疲れをしつつ「自立」に向けて頑張らなければいけない新一年生。
叶う事ならば、ゆっくり時間を割いて、その子のペースで、気持ちに寄り添いながら少しずつ新生活に慣らしていってあげたいものです。
学校のカリキュラムとしては、入学後は割とゆっくり、まずは生活に馴染むことを目標としているように思えます。
参考までにわが子の入学後一週間のスケジュールを掲載します。
| 授業コマ数 | 下校時間 | スケジュールの連絡 | |
|---|---|---|---|
| 1日目 | 2コマ | 11時頃 | 入学式の日 |
| 2日目 | 4コマ | 13時40分ごろ | 入学式の日 |
| 3日目 | 5コマ | 14時ごろ | 2日目の持帰りプリント |
| 4日目 | 4コマ | 13時40分ごろ | 2日目の持帰りプリント |
| 5日目 | 4コマ | 13時40分ごろ | 2日目の持帰りプリント |
| 6日目 | 5コマ | 14時45分ごろ | 2日目の持帰りプリント |
| 7日目 | 5コマ | 14時45分ごろ | 2日目の持帰りプリント |
最初の4月の前半はこのような感じで、下校時間が早いのです。
そして、その情報は入学式以降に随時通知されます。
どのようなタイムスケジュールで新生活が始まるのかが、入学式の日までわからない、入学式の日にも直近二日程度までしかわからないというのがわが子の小学校でした。
母としてはゆっくり新生活に馴染ませてくれるのは嬉しいのです。
でも、働く身としてはもう少し早く先の見通しを立てたいのが本音。
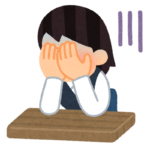
せめて一か月単位の情報が欲しい…!
そして、下校時間が早くて、幼稚園バスの子供たちよりも早く帰宅するのです。
学童保育の終了時間は保育園の閉園より早い!
学童保育の預かり時間は施設によって異なると思いますが、保育園よりも終了時間が早いことが一般的です。
民間企業が運営する民間学童の場合は延長保育も遅くまで可能な所もありますが、数としては学校区にある公立などの学童を利用する方の方が多いと思います。
これもわが子の通う施設の例です。
| 開園時間 | 長期休暇期間 | |
|---|---|---|
| 保育園 | 午前7時~午後8時 | 午前7時~午後8時 ※盆と年末年始のみ特別保育期間有 |
| 学童保育 | 放課後~午後6時30分 | 午前8時30分~午後6時30分 |
延長保育も含んだ時間です。
我が家はまだ下の娘が未就学児なので時短勤務で働いて働いており、送迎時間も対応できていますが、時短勤務が無かったらなかなか厳しいものがあります。

まって!長期休暇の開所時間、私の始業時刻なんだけど!
特に長期休暇(春・夏・冬休み)の開所時間は職場の始業時間と同じなので、送迎していたら遅刻確定です。
ここは対策を検討しなければいけない所です。
職場にフレックスの制度があるか、時短勤務の延長が出来ないか、在宅勤務が可能かなど、お勤め先で出来そうな対策をリサーチする事を強くお勧めします。
また、制度利用が不可能な場合は、お住まいの地域のファミリーサポートの活用も検討すると良いと思います。
学童保育に「他のお子さんがどのようにしているのか」を直接尋ねるのもありだと思います。
娘が通う学童保育では少し大きめの学年(4年生くらい)の子たちは、近所の子たちで集まって開所時間まで公園でひと遊びしてから学童へ向かっている子たちもいました。
また、ご近所で同じ学童のお子さんと数人でグループを組んで、交代でひとりずつ親御さんが付き添って朝を乗りきるご家庭もありました。
私も昨年の夏は、近所のお友達と娘が一緒に歩いて行くのを他の親御さんたちと交代でサポートしていました^^
同じ悩みを抱える保護者の方も多いと思うので、勇気を出して協力をしてみるのもありだと思います!
「メンタル」の壁
子どものメンタル編
年長児になった辺りから、いろいろな所で「来年は小学生だよ」「小学生になったら〇〇」という言葉を様々な場面で聞かされていることでしょう。
プレッシャーをかけるつもりやポジティブな表現であっても、きっと口にすることはあると思います。
それ自体は悪いこととは思いませんが、お子さんの心の中には良し悪しに関わらず、もうすぐ「小学生」とやらになる、という自覚が芽生えているでしょう。
お兄さんお姉さんになるワクワクとともに、未踏の地「小学校」に対して不安や恐れを感じる子もいるかもしれません。
また、生まれて初めて経験する「卒業」に対して、経験した事のない気持ちになり、戸惑っている子もいるかもしれません。
赤ちゃんの頃から当たり前に毎日一緒に過ごしてきたお友達や先生と離れることになります。
幼い子供ながらに様々な事を感じることでしょう。
そして入学後には初めての場所で、知らないお友達がたくさんいて、これまでは自分たちが一番大きなお兄ちゃんお姉ちゃんだったのに、まるで大人のような上級生たちがたくさん。
緊張してしまって、いつも以上に気づかれすることかと思います。

確かに転職したばっかりの時は緊張して、大した仕事してなくてもすごく疲れてたなぁ
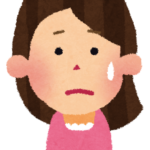
同じ会社内でも、部署移動があるとどうして良いのかわからなかったり、話し相手もいないし
しばらくはのびのび過ごすなんて出来なかったな
入学前後は、いつも元気なお子さんであっても心が疲れる事があります。
なるべく時間に余裕をもって、少しだらっとしたり、ぼけっとする「充電時間」を作ってみてはいかがでしょうか。
親のメンタル編
忘れてはならないのが、親のメンタルにも負担が生じるという事です。
保育園の先生との関係性が良かった場合、保育園はわが子にとっての第二の家のような存在です。
信頼できる先生方との付き合い、毎日の送迎、ちょっとしたお話の時間。
日々忙しい中なので、ゆっくり時間をとって話すことはできないまでも、送迎の時間が重なる保護者の方とはいつしか顔見知りになって挨拶を交わしたり、子供同士が仲良しの場合は子供を通じて交流が生まれることもあったかもしれません。
初めての子育てで、右も左もわからず、思う通りに行かない日々。
働きながら育てることの葛藤もゼロではなかったはずです。
保育園の卒園式は、子の成長を喜ぶとともに、これまで一生懸命子育てをしてきた「親」としても、初めての卒園式です。
感慨深さも並々ならぬものがあると思います。
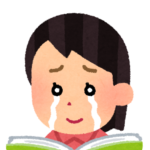
周りの保護者の方も、号泣でしたよ…あんなに泣いたのは久しぶりかも…
そして、子と同じく、未踏の地「小学校」に対する漠然とした不安。
親子共にやっていけるのかという不安など、この時期は本当に心にジェットコースターがあるかのように、様々なことに心が大きく動かされるのでとても疲れると思います。
職種によってはご自身の「異動」などもあり、年度末・年度初めも重なり、この時期のお母さんは本当に大変です。

生活してるだけですごいと思える時期です!本当によくがんばってます!
親子ともに感情をゆさぶられていつも以上に疲れる時期です。
どうか意識的に休息の時間をもうけながら、頑張りすぎずに過ごしてほしいと思います。
まとめ:3つの壁には向き合おう
今回は、全国共通にみられる小1の壁で対策すべき3つの壁についてお話しました。
- 「自立」の壁
- 「時間」の壁
- 「メンタル」の壁
全国共通で現れる課題ではありますが、どれも個人差、家庭差はあると思います。
お子さんの成長と、家庭の事情に合わせて無理のない日々を過ごせることを願っています。
大丈夫です、意外と何とかなるものです!近隣に親族が全くおらず、ママ友もほとんどいないわが家でもその時その時で何とか乗り越えてきました^^
急ぎすぎず、無理しすぎず、意識的に時間を確保しながら
親子ともに小学校入学への準備を進めていただければと思います。