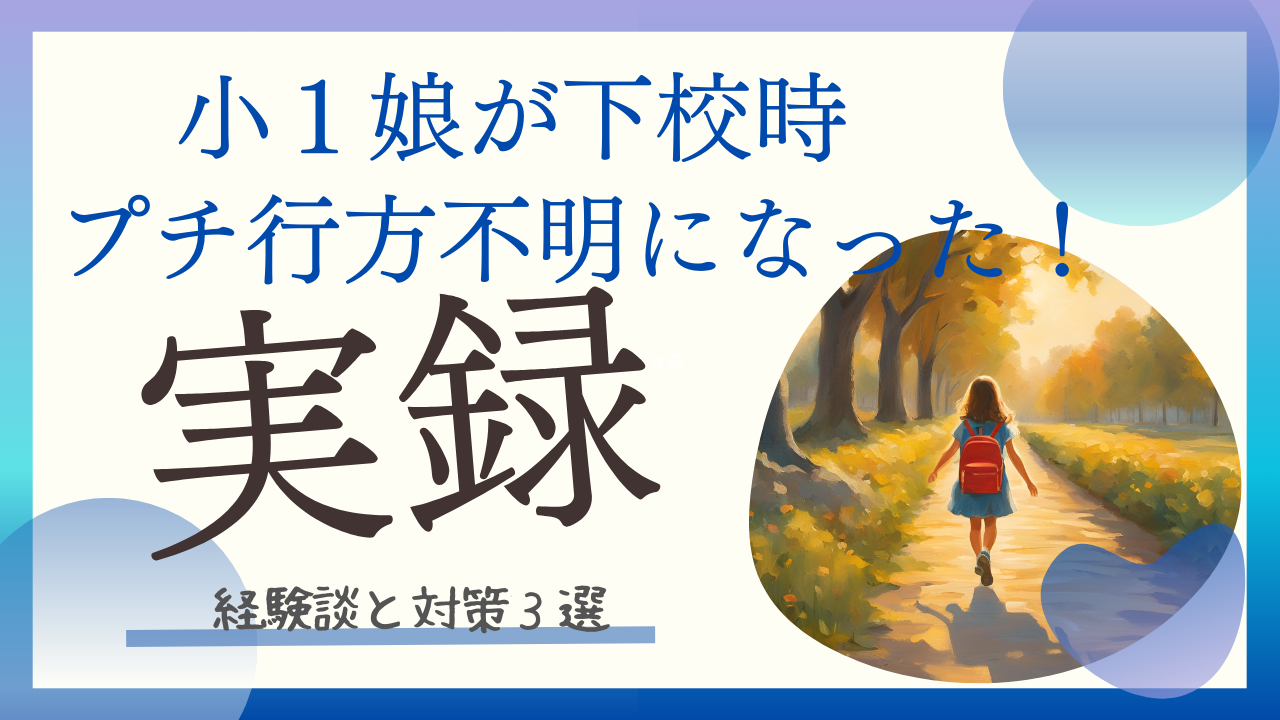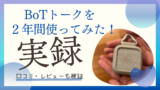小学生の子供にGPSって持たせた方がいいのかな

何かあった時は心配だけど、でも実際はどうなんだろう

実はうちの娘、小学校一年生の5月にプチ行方不明になりました…
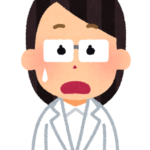
えーっ!
小学生のお子さんをお持ちの親御さんには「GPSやキッズケータイを持たせるかどうか」というお悩みがあるかと思います。
わが家では娘が小学校一年生になってしばらくしてから「BoTトーク」というGPS端末を導入しました。
入学当初は導入せず様子を見ていましたが、しばらくして持たせることに決めました。
今回はGPS導入のきっかけの一つとなった、「プチ行方不明事件」についてお伝えしたいと思います。
小学1年生に実際に起こったトラブルの一例として参考にしていただければと思います。
GPS導入前に起こった「プチ行方不明」事件

下校班で「家へ帰る」ことに憧れていた娘
共働き世帯で、近隣に親族などもいない事から、娘は平日の放課後、毎日学童保育へ行っていました。
娘が利用している学童保育は、小学校の正門から徒歩5分程度の所にありました。
下校時は同じ方角の子供たちで「下校班」を組んでおり、一年生の最初の数か月はその下校班に学校の先生も付き添って下校をする、という形をとっていました。
娘は学童に行くため、同じ学童に行く子たち「学童班」を組んでいました。
しかし、学童をお休みする場合は家の近所の子たちの下校班に入れてもらい、そちらで下校をすることになっていました。

近所の子たちと同じ班で家まで帰ってみたいなぁ…
聞けば、同じ学童に通うお友達の中にも決まった曜日にお休みをしている子もいるらしく、娘はいつもの「学童班」ではない帰宅班で自力で家に帰る事にあこがれを抱いていました。

本当は近所の子たちと家に帰りたいよね…
保育園では両親が共働きなのは当たり前でしたが、小学校では共働きが当たり前ではありません。
家におうちの人がいるため、学校が終わると家へ自分で帰るという子たちの方が多数派でした。
私はそのことを少し後ろめたく感じていたこともあり、仕事の都合がつく日に午後休を取る事にして、その日は学童をお休みして家へ帰ってきてもらうことにしました。
下校班ではじめての帰宅
娘の学校では下校班だけではなく、朝も登校班があり、近所の子供たちと一緒に登校をしています。

登校班の子たちに今日は帰りも一緒って言っとくね!
そう言って、娘は大喜びで学校へ行きました。

ちゃんと班のみんなと一緒に帰ってくるんだよ
一年生の下校時間は早く、この日は14時すぎに下校との事でした。
私は登校班が集合場所にしている家の近くの集会所へ行き、娘たちの下校班の帰りを待つことにしました。
連絡帳に、いつもと違う班で帰宅する旨の連絡もしているし、下校班には学校の先生も付き添いもある。
家から学校まではすぐ近くなので、正直何も心配はしていませんでした。
14時を過ぎたころに集会所の近くまで行くと、同じように子供の帰りを待つお母さんたちの姿がちらほら見えました。
私もその近くで、同じように子供たちの到着を待つことにしました。
しばらくすると、遠くの方から大きなランドセルを背負った小さな子供たちの姿が見え、楽しそうな声が聞こえてきました。
しかし、その集団の中に娘の姿が無かったのです。
下校時に娘がいない?先生も気が付かなかったサイレント失踪
娘の小学校は生徒数も多く、一年生の数もそれなりに居ます。
近所とはいえ、同じ保育園ではなかった子たちや、幼稚園ママ達は知らない顔が多く、同じ班の子がどの子なのか、すぐにわかりませんでした。
さすがにおかしいな、と思っていたころに、集団と一緒に歩いてくる先生の姿が見えました。

こんにちは。1年〇組の△△の母ですが、△△はこの班ではなかったですか?

△△さんですか!一緒に学校を出ましたよ
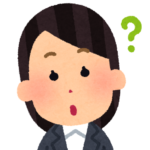
ずっと待っていたのですが、まだ姿が見えなくて…後から来るのでしょうか?

…私が最後尾です。
小学校の方まで続く道に視線を送ると、そこには誰の姿もありませんでした。
帰ってきた子供たちの集団の中に、娘の姿はありません。

…近くを探してきます!
先生も気が付かないうちに、娘は行方ををくらましたのでした。
日傘を畳んで駆け回る!プチ行方不明娘の捜索
笑顔だった先生の顔がすっと真顔になりました。
先生も、別の方向から近くを見てくださるという事でした。念のため学校に戻っていないかの連絡も取ってくれました。
少し前まで日傘をさしてのんびり待ちぼうけをしていたことが嘘のようでした。
住宅街の中を走りながら探し、遠くに見える小学生の後ろ姿の中に娘のランドセルの色を探しますが、見当たりません。
どんどん血の気が引いていきます。
娘の名前を大きな声で呼びながら探し回っていると背後から声がしました。

ママ?どうしたの?
娘が出現しました。きょとんとした顔でこちらを見ています。
心の底からほっとしました。すぐに学校に連絡をして、探してくださった先生とも連絡が取れてお礼と謝罪をしました。
聞けば、一緒に話をしていたお友達が家の方角に曲がる時に一緒についていってしまったとか。
登校時は6学年いるので班を編成する子が本当に近所の子ばかりなのですが、下校時は一学年のみで編成されるため人数が少なく、少し離れた家の子も同じ班になっているそうです。
そのため、途中の曲がり角で随時帰宅していくらしく、元気に「さようならー」とあいさつする娘たちを先生も何の疑いもなく「さようなら」と送り出してくれていたようです。
娘は住宅地の中を私たちと逆方向からちょっと探検しながら帰ってきたそうです。
ほんの十分ちょっとのプチ行方不明事件はこうして無事に幕を閉じました。
プチ行方不明などの下校時トラブルへの対策3選
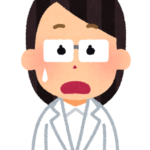
無事に帰って来れてよかったね

本当だよ…うちの近所は道もわかりやすいから家に帰ってこれたからよかったけどね。
正直、気が気じゃなかったよ
わが子の場合は、学校から自宅までが近いことや、道がわかりやすい事などもあり無事に帰宅することが出来ました。
普段から歩いて帰宅をしているお子さんよりも、普段は学童を利用しているお子さんの場合は、通学路に不慣れな場合もあります。
また、いつもと違う行動という嬉しさもあり、テンションが上がってしまい通学路を逸れてしまうこともあるかと思います。
本人たちに迷子の自覚があるかないかはさておき、こうしたトラブルは起こりえるものなのかなと感じました。
そうなった際に慌てずに対応できるよう、対策をいくつかご紹介します
- GPSを持たせておく
- 入学前から通学路やその周辺のお散歩をしておく
- 万が一道に迷ったときにどうするか家庭で決めておく
GPSを持たせておく
一つ目の対策は、GPSなどの端末を持たせておくこと、です。
下校時の寄り道や冒険などにより、一時的に居場所がわからなくなっても、GPSがある事でもしもの時に居場所を確認することが出来て安心感につながります。
わが子はこのプチ事件がきっかけの一つとなり、『BoTトーク』をランドセルに入れることにしました。
端末料金と月々の利用料だけのわかりやすい料金体系で、月500円ちょっとで持たせることが出来るGPSです。
BoTトークを使ってみての感想などはこちらの記事をご覧ください↓↓
小学校や地域によって、GPS端末などは学校への持ち込みのルールが異なる場合がありますので、ご確認ください。
入学前から通学路やその周辺のお散歩をしておく
少し道に迷ったとしても、なんとなくの方向感覚や土地勘があると、自力で帰宅することが可能です。
私も入学前に通学路やその周辺を一緒にお散歩していました。
意外と盲点なのが「通学路以外の近所」です。どんなに家の近所であっても、普段通らない場所であれば迷子になる可能性はあります。
ぜひお散歩をして、家の方向を示す目印になるようなものをお子さんと一緒に覚えてみてください。

うちの近所には民家ばっかりで、目印になるような建物なんてないよ
大きな建物や目立つものでなくても、お子さんの目線から確認出来るものであれば何を目印にしても大丈夫です。
可愛い置物があるお家や、黒い壁の家、郵便ポストなど、なんでもオッケーです。
ぜひ、お子さんと通学とその周辺を散歩して目印を見つけたり、土地勘を身に着けてください。
万が一道に迷ったときにどうするか家庭で決めておく
それでも「まさか」が起こることはあります。
そんな時のために、万が一に備えた対策をご家庭で話し合って決めておくことも大切かと思います。
これは迷子に限らず、家族の事故や病気などの緊急事態が起こった場合や、災害が発生した時にも役に立つと思います。
もしもの時の対応策の一例をあげます。
- 学校に戻って職員室の先生に声をかける
- 交番へ行ってお巡りさんに事情を話す
- 近所のスーパーやコンビニへ一時避難
- 絶対にたどり着けるお友達の家や習い事の教室へ行く
わが家の場合は、徒歩圏内に学校、交番、スーパー、コンビニがあるためこれらをあげました。
「わかる場所に行って待機する」が基本方針です。
GPSのトーク機能に加えて、私の携帯電話の番号を覚えさせているため、電話が借りられる場所であれば連絡も可能です。
それらに加えて、両親に何かトラブルがあった場合などはお友達の家へ助けを求めるようにも伝えています。
まとめ
今回は小学1年生の時に実際に経験した「プチ行方不明事件」と、その対策3選をご紹介しました。
ご家庭や、住まわれている環境によってもどんな対策が良いかはそれぞれ違う事かと思います。
ぜひご家庭で一度話し合って、「もしも」「まさか」のトラブルに備えた対応策を準備していただければと思います。